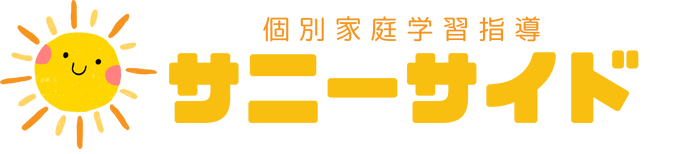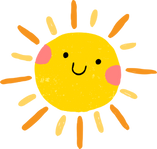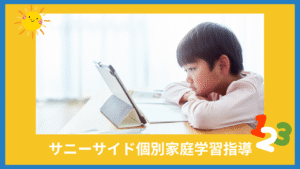幼児期(1歳から5歳頃まで)は、子どもの成長と発達が著しい時期であり、食生活が身体的および精神的な健康に与える影響は非常に大きいです。
この時期の食生活は、将来の健康や生活習慣にまで関わるため、特に注意が必要です。
今回は、幼児期の食生活の重要性についてお話できればと思います。
幼児期は、身体の成長が著しい時期であり、適切な栄養素の摂取が不可欠です。特に以下の栄養素が重要です。
タンパク質:筋肉や組織の成長に必要。
- 動物性たんぱく質:豚肉、鶏肉、牛肉、イワシやアジの干物、マグロやカツオなどの赤身魚、サケやサバ、卵
- 植物性たんぱく質:大豆を使った豆腐・納豆、枝豆
- 乳製品:牛乳・チーズ・ヨーグルト
カルシウムとビタミンD:骨や歯の発達を促進。
- 牛乳や乳製品、豆腐や納豆などの大豆製品
- ひじき・わかめ・のりなどの海藻類
- 小松菜や青梗菜などの緑黄色野菜
鉄分:脳の発達や酸素の運搬に関与。
- 動物性食品:あさり・レバー・さんま
- 植物性食品:がんもどき・豆乳・小松菜
ビタミンA、C、E:免疫力の向上と健康維持。
- 野菜:赤ピーマン・トマト・ブロッコリー
- 果物:柿・キウイフルーツ・いちごなどの季節のもの
- 芋類:サツマイモ・じゃがいも
- ナッツ類:アーモンド・くるみ
- 魚類:ニジマス・サケ・サバ・サンマ・ウナギ
これらの栄養素をバランスよく摂取することが大事なのですが、栄養素の中でも動物性のものと植物性のものがあります。
こちらもバランスよく摂取することをお勧めします。
これら全てを考えながら食事を用意するのは難しいですよね。
とにかく色々な食品をバランスよく摂取するということを頭に置いていただければいいと思います。
食習慣の形成 幼児期は、一生の食習慣が形成される重要な時期です。この時期に身につけた食習慣は、成人後の健康にも影響を与えます。
多様な食品の経験:
さまざまな食品を経験させることで、偏食を防ぎます。
そもそも親の私たちに好き嫌いがあると、子どもにも大きく影響してしまいます。
大人の私たちから普段の食生活において気をつけなければなりませんね。
規則正しい食事:
食事のリズムを整えることで、消化吸収がスムーズになります。
家族での食事:
親の食事行動が子どもに影響を与えるため、家族で楽しく食事を摂ることが大切です。
なかなか家族全員揃っての食事は難しいかもしれませんが、食事中に新聞を読んでいる、スマホで動画などを見ているという環境ではなく、食事中こそその日にあった出来事や困っていることを話して意見を言ったり、時事問題について家族で話し合うなど、楽しく有効に食事時間を過ごしていただきたいと思います。
心身の発達との関係 栄養バランスの取れた食生活は、身体だけでなく心の健康にも影響を与えます。
集中力の向上:
ビタミンB群や鉄分の摂取は、集中力や記憶力の向上に寄与します。
情緒の安定:
オメガ3脂肪酸やビタミンDは、精神的安定に関係します。
運動能力の向上:
適切なエネルギー摂取は、運動能力や体力の向上に役立ちます。
家庭環境と食生活 幼児期の食生活は、家庭環境によって大きく左右されます。
親の関与:
親が食事作りや食事のマナーを教えることが大切です。
忙しい現代において一緒に作ったりなど、大変ではありますが、お子さまとの会話時間として捉えながら過ごすと、楽しいかもしれませんね。
食育の実践:
子どもと一緒に食材を選んだり、調理に参加させることで、食への関心が高まります。
そうすると、食だけではなく他の物事への興味・関心も高まりやすくなり、どんどん勉強(知識)意欲が高まります。
過度な制限の回避:
甘いものやジャンクフードを完全に禁止するのではなく、適度に楽しむ工夫も必要です。
ここでオススメ朝ごはんをご紹介
朝ごはんはとても大事ですよね?それは分かっているけど時間がない朝は時短目的・栄養素のバランスもいいはず!と思って「グラノーラ」を出していませんか?
ものによって色々ですが、いわゆる美味しいグラノーラには大量の甘味料が含まれています。
それを摂取すると、血糖値が急上昇!急上昇するということは急降下する。
急降下するときに空腹感を感じ、イライラする。
これは悪循環になっています。
それを回避するには、「和食」!!ごはんに卵焼き・お味噌汁・ぬか漬けの漬物。これが一番!
何がいいのかというと、血糖値の急上昇を抑えることができます。急上昇しないので、急降下もしない。
血糖値が一定に保たれているので、気分のブレもなくなります。
これはお子さまだけではなく、大人の私たちにとっても大切なことですよね。
これを機に、私たち大人も朝ごはんの習慣を考え直してみてはいかがでしょうか?
まとめ
幼児期の食生活は、身体的成長だけでなく、心の健康や将来の生活習慣にも深く関わります。
親や保護者は、バランスの取れた食事を提供し、子どもが健康的な食習慣を身につけられるようサポートすることが重要です。
食生活が整っていると、頭も冴え、全てのサイクルがうまく回ります。
適切食な食生活を通じて、子どもの健やかな成長を促しましょう。