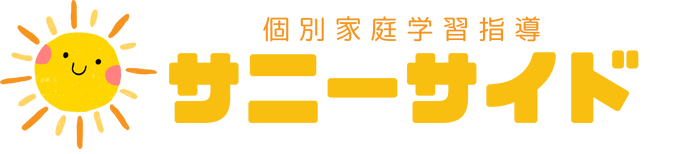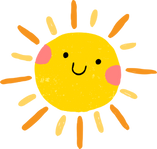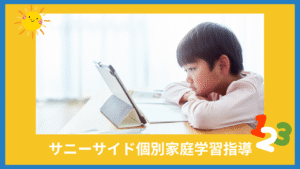近年、子どもの安全を確保するために、さまざまな対策が取られています。例えば、子ども用のはさみや包丁、食べられるクレヨン、幼稚園の柔らかい壁、指を挟んでも痛くない窓の冊子などが挙げられます。これらは一見、子どもを危険から守るための優れた対策のように思えますが、果たして長期的な視点で見たときに本当に良い影響をもたらしているのでしょうか?
私は、極端なことは言いたありませんが、これらの商品が「とても良いもの!!」とも思いません。
子どもの本当の意味での成長を促すには・・・?
ぜひ一緒に考えてみませんか?
1. 「学びの機会」の喪失
子どもは成長する過程でさまざまなことを経験し、学んでいきます。転んで痛みを感じたり、はさみで指を少し切ってしまったりすることも、その一環です。こうした経験を通じて、子どもは「次からはもっと注意しよう」と学び、危険を回避する能力を身につけます。
しかし、すべての危険が排除された環境では、このような学びの機会が失われてしまいます。例えば、「指を切らないようにするにはどうすればよいか?」を学ぶことなく、ただ安全な道具を与えられているだけでは、実際に危険な場面に遭遇したときに適切に対処できなくなる可能性があります。
2. 自己責任感と判断力の低下
過度に保護された環境で育った子どもは、自分で判断し、責任を持つ経験が乏しくなります。例えば、「窓の冊子に指を挟んだら痛い」という経験がない子どもは、大人になってから危険を察知する力が十分に育っていない可能性があります。その場所では安全だったとしても、違う場所では安全はなくなってしまう。
それ故にお友達の指を挟んでしまって怪我をさせてしまうかもしれません。
また、何か問題が起きた際に「誰かが助けてくれる」「環境が安全だから問題ない」という考えを持つようになると、自ら考えて行動する力が育まれません。その結果、社会に出たときに自己責任の意識が希薄になり、問題に直面した際に適切な対処ができなくなるリスクがあります。
3. 精神的な強さの育成不足
子どもは小さな失敗や痛みを経験しながら、精神的に強くなっていきます。しかし、すべてのリスクが取り除かれた環境では、こうした成長の機会が奪われてしまいます。
例えば、転んでもクッション性の高い床であれば痛みを感じることなく、何度転んでも「転ぶことの怖さ」や「どうすれば転ばないか」を学ぶ機会が減ってしまいます。同様に、刃物で指を切るリスクがないと、「刃物は慎重に扱うもの」という意識が育ちにくくなります。
精神的な強さは、小さな失敗や痛みを乗り越えることで形成されます。その機会が奪われた子どもは、大人になったときに困難を乗り越える力が不足し、ストレス耐性が低くなる可能性があります。
4. 「安全すぎる環境」による好奇心の抑制
子どもは、未知のものに対する好奇心を持っています。しかし、過度に安全な環境で育つと、その好奇心が抑制されることがあります。
例えば、「危険だから触ってはいけない」「これは使ってはいけない」といった制限が多い環境では、子どもは新しいことに挑戦する機会が減り、結果としてチャレンジ精神が育ちにくくなります。
また、安全な環境に慣れてしまうと、好奇心を持って何かを試すことに対して慎重になりすぎたり、リスクを伴う行動を避けるようになる可能性があります。これにより、創造力や問題解決能力の発達が妨げられることも考えられます。
5. バランスの取れた幼児教育の重要性
もちろん、子どもの命を守るために一定の安全対策は必要です。しかし、そのバランスが重要だと思います。完全にリスクを排除するのではなく、「適度な危険を伴う環境」を提供することが、子どもの成長には欠かせません。
例えば、包丁の扱い方を学ぶために「本物の包丁」を使うことは重要ですが、その際に適切な指導を行うことが必要です。大人がそばについて使い方を教えたり、最初は小さな野菜を切るなどの段階を踏むことで、子どもは安全に包丁を扱う術を身につけることができます。
また、遊び場においても、適度な挑戦ができる環境を整えることが重要です。最近では、過度に安全な遊具ばかりが設置されている公園もありますが、子どもが自ら工夫して遊べるような遊具や、多少のリスクを伴う遊びができる環境を整えることが、成長には有益です。
6. まとめ
過度な保護教育は、子どもを一時的に安全にするかもしれませんが、長期的に見ると自己判断力の低下、責任感の欠如、ストレス耐性の低下など、多くの問題を引き起こす可能性があると考えます。
重要なのは、「リスクを完全になくすこと」ではなく、「リスクと向き合い、それを乗り越える力を育むこと」です。そのためには、大人が適切にサポートしながら、子ども自身が経験を通じて学べる環境を整えていくことが求められます。
幼稚園などたくさんの子どもたちを見る環境下では安全を第一に考えるのも理解できます。
ただ、お家ではぜひ「本物」に触れて、「危険」を知り、「安全に使うには」ということをお話してあげてもらいたいと思います。
子どもたちが将来、社会で自立し、困難に立ち向かう力を持つためには、適度な危険を許容し、その中で学ばせる教育が不可欠です。我々大人は、子どもを守ることと、成長の機会を奪わないことのバランスを慎重に考える必要があるのではないでしょうか。