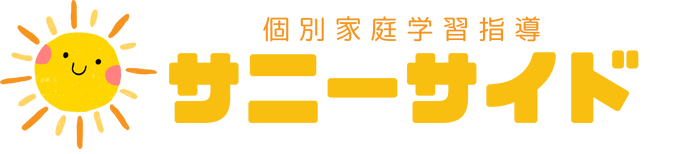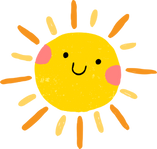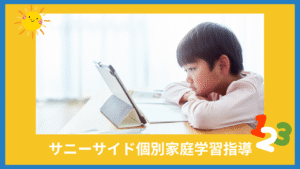4月に入り、お子さまたちの新生活、戸惑ったり大変だなと感じる毎日かもしれません。
その中でも、少しでも楽しい!と感じることを見つけて、それを楽しんでいると大変だと思っていたことがなくなったりもします。
さて、楽しみといえば、遊びです。
今回はそんな遊びの中からとても大事な能の発達についてのお話です。
幼児期は、人間の一生の中でもっとも成長著しい時期です。言葉を覚え、体を動かし、人と関わりながら、心身ともに急速に発達していきます。この大切な時期に、子どもがどのような体験をするかは、将来の学びや人間関係、さらには生きる力そのものに大きな影響を与えるのではないでしょうか。その中でも、私が重要視しているのは「指先を使った運動」です。手や指を使った運動は、単に楽しい!ではなく、子どもの脳や身体、そして心の発達に深く関わっていくと考えます。
そんな指先の運動に関する記事を書いてみました。
指先を使うことは「脳を使うこと」
指先の動きは、大脳の運動野や感覚野と密接につながっています。特に人間の脳は、指先の繊細な動きを制御するために非常に広い領域を使っており、指を使えば使うほど脳は刺激され、発達していきます。たとえば、折り紙を折る、ひもを通す、粘土をこねるといった活動は、視覚情報と手の動きを連携させながら、集中力と手先の器用さを養うことにつながります。
これらの活動を通して、子どもたちは「どうすれば上手くできるか」を試行錯誤し、自分の動きをコントロールする力を身につけていきます。この過程こそが、創造力や問題解決能力の育成に直結すると考えます。
幼児期における代表的な指先遊び
指先を使った遊びにはさまざまな種類があります。以下に、幼児教育で取り入れられている代表的なものを紹介します。
積み木遊び
大小さまざまなブロックを積んだり崩したりする遊びは、手のひら全体だけでなく、細かい指の使い方も要求されます。バランス感覚や空間認知能力、創造力も育ちます。
どれだけ高くブロックを積み上げられるか、ブロックを繋げてどんどん形を造っていく。それだけでも子どもたちの脳に物凄い刺激があります。
ビーズ通し・ひも通し
ひもに小さなビーズを通すこの遊びは、視覚と手の協応動作(手と目の連動)を必要とし、集中力と指先の器用さを高めるのに最適です。
穴がたくさん開いた板にひもを通していく、いわゆる縫物のような遊びです。「どうすれば短いひもで形をつくれるのか」そして出来上がった作品から今度はひもを解いていくという作業もまた指先と脳の活性化に繋がります。
最初は紐が絡まって癇癪を起すお子さまもいるでしょう。
そんな時はゆっくり「どうなっているからひもが絡んでいるのか、どうしたらそのひもが解けるのか」ということを、時間の許す限り、お子さまと一緒に考え・導いてあげてください。
粘土遊び
自由に形を作れる粘土は、創造性を刺激するだけでなく、指先の感覚や力加減を学ぶ訓練にもなります。触感の違いを感じることで、感覚統合の発達も促されます。
粘土にもたくさんの種類があります。ぜひ色々な種類の粘土を触ってみて、その感触も楽しんでみてください。
折り紙や切り紙
お年寄りのリハビリにも使われる折り紙。紙を折る、切る、貼るといった一連の動作には、順序立てて考える力や、細かな手先のコントロールが必要です。また、完成させた達成感は、子どもの自己肯定感を高める要因になります。
「ピッタリ紙を合わせる」指一本ではできない繊細な動きが脳の発達に大きく影響します。
各季節・お子さんの興味のあるものなど、ぜひ一緒に楽しんでみてください。
砂場での遊び
公園や園の砂場、そして庭での土遊び、どれも大切な遊びです。
土の中には虫もいて、、、。虫の苦手な人にとっては大変かもしれませんが、その虫から話がたくさんできますね。
季節の話、その虫を一緒に本で調べたりと、たくさんのコミュニケーションが生まれます。
砂場でつくるお山、そしてトンネル。どうやったら上手くトンネルが造れるのか。
両側からお友達や親御さんと創り上げていって、トンネルの中で手が繋がった時の喜びに溢れる子どもの顔は今でも大切な私の思い出です。
汚れていい、目に少し砂が入ってもいい。ちゃんとし対処は必要ですが、少々のことは子どもの成長を思ったら小さなことだと私は思います。
指先遊びがもたらす心の成長
指先を使った遊びは、身体的な発達だけでなく、子どもの心にも良い影響を与えます。たとえば、手作業には集中力が必要ですが、この集中する時間が子どもの「心の安定」をもたらします。現代の子どもたちは、刺激の多い環境の中で、注意散漫になりやすい傾向があります。しかし、静かな環境でじっくりと何かを作る時間は、心を落ち着かせ、自分と向き合う機会になります。
また、失敗しても工夫してやり直すことで、粘り強さや自己解決能力も養われます。そして完成した作品を「見て見て!」と大人に見せることで、他者とのコミュニケーション力や達成感、承認される喜びも感じられます。
デジタル時代だからこそ必要な「手の経験」
現代社会では、子どもが幼い頃からタブレットやスマートフォンに触れる機会が増えています。デジタル技術の進歩により、知識の習得や情報へのアクセスは格段に向上しましたが、その一方で、実際に「手を使う」経験が減ってしまっているという指摘もあります。画面をタップするだけの動作では、手のひらや指先の発達は十分に促されません。
だからこそ、意識的に「手でものを作る」「手を動かして遊ぶ」時間を確保することが、これからの幼児教育においてますます重要になってきます。五感を使った体験が豊富な子どもほど、私が日々大切にしている「思考力・推理力」「空間認知能力」の感性が育まれやすくなります。
便利なタブレットも活用しつつ、それでは足りない部分に関しては時間や手間を惜しまず、子どもたちと向き合う時間もどうか大切にしてください。
保護者、大人の役割
子どもが指先を使った遊びに取り組むためには、大人の関わりが不可欠です。まず、子どもにとって魅力的な遊びの環境を整えることが大切です。安全で多様な素材を用意し、「やってみたい」という気持ちを引き出す声かけや見守りが、子どもの主体的な活動を支えます。
また、成果や上手さを評価するのではなく、「がんばっているね」「工夫したね」といったプロセスを認める声かけをすることで、子どもは自分の手で世界を広げていく喜びを感じられます。
どうしても大人の手を借りないとできない作業もあります。
そんな時は最後の最後のちょっとした作業を子どもにさせてあげてください。
「最後」のひとつをやるだけで、子どもは「自分でできた!」といい勘違いをします。
このいい勘違いから喜びや成果を感じ取れるのです。
まとめ
指先を使った遊びは、単なる「手遊び」ではなく、子どもの脳と心と体の発達に深く関わる重要な教育的要素です。幼児期に多くの指先活動を経験することは、その後の学習の基盤となる力、そして人間関係や感情のコントロールといった非認知能力の育成にもつながります。
デジタル技術の進展が進む現代だからこそ、「手を動かす」原始的で本質的な遊びの価値を再認識し、子どもたちに豊かな手の体験を提供していくことが、私たち大人の大切な役割だと思います。
デジタルと原始的な部分の両方をバランスよく、上手に使っていきましょう。