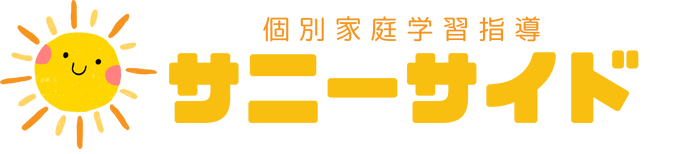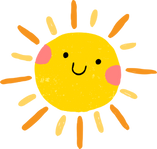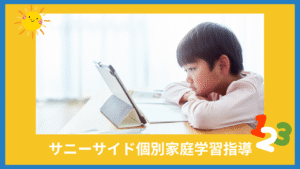幼児期は、人としての土台を築く非常に大切な時期です。言葉を覚え、感情を知り、社会との関わり方を学ぶこの時期に、「対話」はとても大きな意味を持ちます。そして、特に重要なのが、同世代の子どもたちだけでなく、異なる世代の人たち――大人や高齢者、兄弟姉妹など――との関わりの中での対話です。こうした多世代との対話は、子どもたちの心と身体の成長に多様な良い影響をもたらします。
今回はそんな言葉・会話の大切さについてお話したいと思います。
1. 多世代との対話が育むもの
言語能力の発達
子どもは会話を通じて言葉を覚えます。親や保育士、祖父母、年上の子どもたちとの対話は、それぞれに違った言葉遣いや表現があり、それらを吸収することで語彙が増え、言葉の使い分けも学んでいきます。幼児同士では使わないような丁寧な言い回しや敬語に触れることも、大人との対話の中では自然と体験できます。
祖父母と一緒に住んでお子さんは、いわゆる昔の言葉をよく知っています。
学校教育でわざわざ「習う言葉」を普段の生活の中で習得できるのは、祖父母と長い時間を過ごしているお子さまの特権でね。
社会性の基礎を築く
異なる年齢や立場の人と関わることで、子どもは「相手に合わせた振る舞い」を学びます。たとえば、おじいちゃんおばあちゃんにはゆっくり話す、大人の話を静かに聞く、小さな子にはやさしくする……といった経験を通して、思いやりや協調性が育まれていきます。これは、集団生活の中でとても大切な社会性の基盤になります。
こうやってコミュニケーション能力は発達するのです。
自己肯定感の向上
大人との対話の中で、子どもが「ちゃんと話を聞いてもらえた」「自分の意見が認められた」と感じることは、大きな自信につながります。特に、世代が離れた人に優しく接してもらったり、ほめてもらったりする体験は、子どもにとって心に残る特別なものになります。
これは同世代のコミュニティだけでは味わえないものの一つだと思います。
2. 家庭内での多世代対話の役割
現代では核家族化が進み、祖父母と一緒に住んでいる家庭が少なくなっています。
では、祖父母と一緒に住んでいる子どもだけの特権なのか?
そうではありません。帰省時やオンライン通話などを通じて祖父母と会話を増やしてみたり、お年寄りと積極的に会話してみることは、子どもにとって貴重な経験となります。
祖父母世代は、ゆったりとしたテンポで会話を楽しむ傾向があり、せかせかしがちな現代の生活の中で、子どもが「待つこと」「聞くこと」を学ぶ良い機会になります。また、昔話や経験談を聞くことで、子どもは時間の感覚や歴史に触れるきっかけにもなります。
それこそが、学校教育を超えてできる「生活の中での学習」です。
3. 保育・幼稚園での異世代交流の意義
保育園や幼稚園でも、地域の高齢者との交流を取り入れる取り組みが増えてきています。例えば、近所の老人ホームを訪問したり、地域のボランティアのお年寄りが絵本を読み聞かせたりする活動です。
これらの活動を通じて子どもは、高齢者のやさしさや穏やかな雰囲気に触れると同時に、「人は年をとるもの」「お年寄りには敬意を持って接する」という自然な価値観を身につけていきます。
また、高齢者にとっても、子どもとの交流は大きな生きがいになります。互いが心を通わせることで、世代を超えた「共育(ともいく)」の関係が生まれるのです。
4. 地域とのつながりと、多様な人との会話
昔ながらの地域社会では、子どもが近所のおじさんやおばさんに声をかけられることが日常でした。しかし、現代では防犯意識の高まりなどから、地域の人との接点が少なくなっています。
少し寂しく思えますね。
とはいえ、地域の行事やお祭り、清掃活動など、少しでも地域の人と顔を合わせる機会を大切にすることは、子どもにとって「社会の中での自分の位置」を知る貴重な体験となります。親子で地域の活動に参加し、いろんな世代の人と話す姿を子どもに見せることも、「対話」の学びにつながり、「コミュニケーション能力」もしっかりと身に付いてきます。
5. 異世代間の対話を豊かにするための工夫
聞き上手になる
子どもに話しかけるときは、まず「聞く姿勢」を大人が持つことが大切です。子どもの話を否定せず、じっくり耳を傾けることで、子どもは安心して自分の思いや考えを話せるようになります。
子ども扱いしすぎない
つい「まだ小さいからわからない」と決めつけがちですが、子どもは想像以上に多くのことを感じ、考えています。丁寧な言葉で説明したり、質問にしっかり答えたりすることで、子どもも「ちゃんと話していいんだ」と感じ、自信を持つことができます。
多様な話題を楽しむ
季節の話、食べ物の話、動物や自然の話、昔のこと……子どもと大人では興味の対象が違うことが多いですが、共通点を探しながら話題を広げていくことも対話力を育てます。絵本や写真、昔の道具などを使って、話題のきっかけをつくるのも効果的です。
そして、ちょっとした工夫でもっとたくさんのことを学べます。
例えば、一緒にお買い物に行った時には季節の食材について話をしながら購入して、献立を一緒に考えてみたり、
散歩しながら、季節の花や草について「会話」する。
日常の些細な「会話」で勉強はできるのです。
違う投稿でもお伝えしていると思いますが、机上の勉強が全てではなく、むしろ日常生活からの勉強の方が子どもは頭に入ってきますし、経験を通じて得た知識は机上の知識よりも定着します。
6. 多世代の対話が子どもに与える未来への力
今の子どもたちが育つ社会は、多様性にあふれた時代です。年齢だけでなく、国籍、文化、考え方の違う人たちと関わる機会がますます増えていくでしょう。そうした中で必要になるのは、「自分とは違う相手と向き合い、対話を通じて理解し合う力」です。
異世代の人との対話経験は、この力の土台になります。「年上の人の話を聞く」「年下の子に教える」「年の離れた相手とも心を通わせる」という経験を幼児期から積み重ねることは、将来のコミュニケーション脳力や社会適応力に直結します。
最近園で「縦割り教育」という言葉をよく耳にします。
年長さんが年少さんのお世話をしたり、縦での教育がされています。
とても良いことだと思います。
終わりに
幼児期の子どもたちにとって、多世代との対話はただの「おしゃべり」ではありません。それは、言葉を学び、人との関係を築き、自分を表現し、相手を理解するためのかけがえのない学びの場です。
ついついスマホを見ている時間が長くなっているこの時代。ぜひこれを機会に子どもとの会話をもっともっと楽しんで、大きな学びとしてみてください。