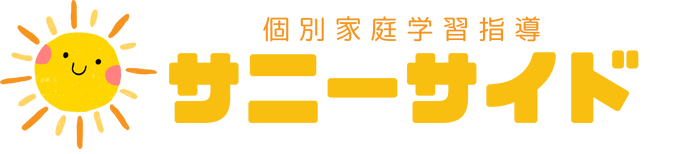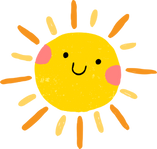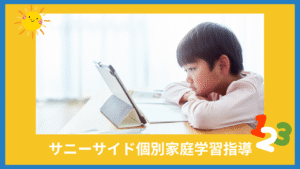幼児期は、人間の基礎的な能力や習慣が形成される極めて重要な時期です。この時期に身につける生活習慣や運動能力は、その後の成長や学習に大きな影響を及ぼします。その中でも、「お箸」と「鉛筆」の持ち方は、幼児教育における基礎的な指導項目として非常に重要ですし、お子さまの能力アップにも影響すると考えます。
今回は「持ち方」についてお話したいと思います。
お箸の持ち方の重要性
1. 手指の巧緻性を高める
お箸を正しく持つことは、指先の器用さ(巧緻性)を育てるのに最適な方法の一つです。正しい持ち方を習得するには、親指・人差し指・中指を適切に使い分ける必要があり、これにより微細な動作のコントロール能力が向上します。巧緻性が高まると、他の細かい作業(ボタンをとめる、紐を結ぶ、ハサミを使うなど)にも良い影響を及ぼします。
手や指の神経は脳と密接につながっているため、手先を動かすと脳が刺激されます。
以前の投稿にもありますが、指先の運動は本当に大切です。
2. 食事の姿勢とマナーの基本
お箸の正しい使い方は、単に食べ物を口に運ぶ手段としてだけでなく、食事中の姿勢やマナーにも関係します。正しく持てないと、身体を前に倒したり、食器を持ち上げたりといった不自然な姿勢になりがちです。また、日本の文化において、お箸の使い方は「しつけ」の一環としても重視されており、家庭や社会の中での基本的なマナーを学ぶきっかけにもなります。
少し話がずれますが、友人や仕事関係の方と食事をする際、相手の食事の仕方を見てがっかりしたり、「やっぱりこの人は人間的にも素晴らしい人だな」と感じたりします。
クチャクチャと音を立てて食事をしたり、お箸を持ったままジェスチャーをしながら話をしたり、肘をつきながら食べたり。そんは大人いないでしょ!!と思われるかもしれませんが、実際います。
そして、その方はお子さんがいらっしゃいます。多分ご自身がマナー的に間違ったことをしているとは思っていないでしょう。しかし、そのお子さんは大切なマナーを教えられないまま育つんだろうなと思うと、残念です。
皆さんも、もう一度自身を振り返ってみてくださいね。
私も、また改めて自分の「食べ方」を見直したいと思います。
3. 自己肯定感の向上
お箸を正しく使えるようになることで、「自分でできた!」という成功体験を子どもに与えることができます。このような達成感は、自己肯定感の土台となり、他の学習や生活習慣の自立にも好影響を及ぼします。
鉛筆の持ち方の重要性
1. 書字能力の基礎を作る
鉛筆の正しい持ち方は、文字を書くための第一歩です。筆圧や線のコントロール、手の動かし方など、すべての書字動作は正しい持ち方から始まります。誤った持ち方を習慣化してしまうと、後から直すのが難しくなるだけでなく、字が汚くなる、長時間書くと疲れる、手が痛くなるといった問題が発生しやすくなります。
幼いお子さんは、まだ力がなくて、指三本で鉛筆を持つことがあります。
ですが、三本の指で鉛筆を持つと、どうしても手首の可動域が狭くなります。
塗り絵をしてみてください。上手に鉛筆を持てているお子さんは手首が柔らかく動いていて、色も上手に塗れているはずです。
2. 学習の集中力と持続力に影響
鉛筆の持ち方が正しくないと、筆記中に余分な力が入ったり、不自然な姿勢をとったりして、集中力が途切れがちになります。逆に、持ち方が正しければ、無理のない姿勢で長時間集中して書くことが可能になります。これは、就学後の学習にも直結する大切なポイントです。
3. 成功体験と達成感の積み重ね
自分の名前をきれいに書けたとき、文字が上手になったと褒められたとき、子どもは大きな喜びを感じます。その喜びは、書くことへの意欲につながり、さらなる学びの原動力となります。正しい鉛筆の持ち方は、そうした成功体験の「入口」となるのです。
持ち方指導のタイミングとアプローチ
1. タイミングは「興味を持ち始めた時」がベスト
子どもによって成長のスピードはさまざまですが、一般的には3〜5歳頃からお箸や鉛筆への興味が高まってきます。この時期に「正しい持ち方」を意識して教えることが、自然な習得につながります。
とにかくクセがつく前に、直してあげないと、後で修正するのは難しいですし、時間もかかります。
2. 遊びや生活の中で無理なく教える
「練習しなさい」と強制するよりも、遊びや生活の中に取り入れて楽しく学ぶことが効果的です。たとえば、豆をお箸で掴んだり色鉛筆でお絵描きをする中で、自然とさりげなくアプローチしてあげることが大切です。
3. 保護者・教育者の協力が不可欠
正しい持ち方の習得には、周囲の大人の理解と協力が欠かせません。家庭と園・学校での指導が連携していることが理想です。一方では正しい持ち方を教えているのに、一方では見ていなくて、間違った持ち方をしていても注意しないというケースもあります。
正しい持ち方をサポートする道具の活用
現在では、正しい持ち方をサポートする様々な補助具が市販されています。お箸補助具(持ち方矯正グッズ)や、鉛筆の持ち方補助グリップなどを活用することで、自然と理想的な指の配置を学ぶことができます。ただし、補助具に頼りすぎるのではなく、あくまで「補助」として使用することが望ましいです。
最後に:一生の宝になる「正しい持ち方」
お箸や鉛筆の持ち方は、幼少期に正しく身につけることで、その後の生活にわたって大きなメリットをもたらします。見た目の美しさや姿勢だけでなく、身体の使い方、集中力、そして自己肯定感にまで影響を与える重要な基礎スキルです。
「食べ方が美しい」「鉛筆を正しく持って字が綺麗」「姿勢が美しい」これは男女問わず大人になってからも宝となります。
ぜひ、今一度お子さまの「持ち方」をチェックしてみてください。