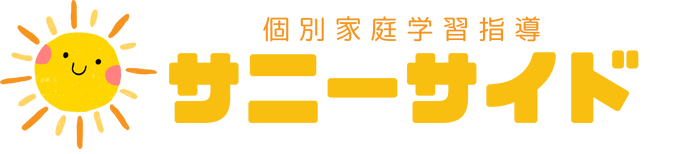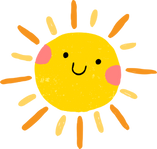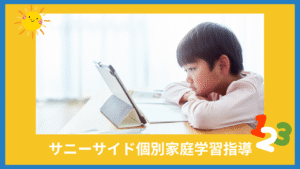幼児期は、子どもの脳や身体の成長が著しく、基礎的な能力が形成される非常に大切な時期です。言葉や数に親しみはじめ、自分の名前を書いたり、数字を覚えたりするこの時期に、「書く」という行為は学びの入り口として重要な意味を持ちます。そして、文字や数字を「書く」際に軽視されがちなのが「書き順」です。
書き順は単なる形式的なルールではなく、子どもの成長や学習の土台を支える重要な要素です。今回は、なぜ書き順が幼児教育において大切なのか、そしてどのように日々の生活の中で声掛けしていけばいいのかなど、お話できればと思います。
1. 書き順は「読みやすさ」と「美しさ」の基本
書き順は、日本語において長年にわたり体系化されてきた、合理的なルールです。ひらがな・漢字・数字それぞれに、最も自然で無理のない書き方が定められており、それに従うことで文字は整い、読みやすくなります。
たとえば、「ひらがな」の「き」「さ」「も」「な」など、書き順を間違えると形が崩れやすいですね。
また、「漢字」では、部首と構成のバランスを意識した書き順で書くことで、左右・上下の整いが生まれ、見やすく美しい文字が身につきます。
毛筆でひらがなや漢字を書くとわかりやすのですが、書き順はこの文字を書く「流れ」になっています。
書き順を誤って毛筆で書くと、次に繋がらないので、バランスの悪い字になってしいます。
幼児期に正しい書き順を習得しておくことで、その後の学習がスムーズに進み、「ていねいに書く」習慣も自然と身につきます。
2. 正しい書き順は「運筆力(うんぴつりょく)」を育てる
運筆力とは、鉛筆やペンを使って線を思い通りに動かす力のことです。書き順に沿って文字を書くことは、無理のない自然な動きで筆順をたどる練習になり、スムーズな筆使いと筆圧のコントロールを身につけることにつながります。
誤った書き順で書いていると、筆の動きがぎこちなくなり、書くこと自体に疲れやストレスを感じてしまう子どももいます。結果として、書くことが嫌いになったり、字が乱れたりする原因になることもあります。
特に、曲線の多いひらがなや複雑な画数を持つ漢字では、正しい順番で筆を運ぶことが、美しい文字を書く力を養うために非常に重要です。
この「運筆力」というのは、前回の投稿「お箸や鉛筆の持ち方は能力アップの鍵?!」の回にもあるように、持ち方も勿論大事ですが、正しい持ち方をしていても書き順を誤ってしまうと、せっかくの運筆力が半減してしまいます。
3. 書き順の習得は「集中力」と「注意力」を高める
文字を書くという行為には、目と手の協調運動、脳の情報処理、そして空間認識など、複数の機能が同時に関わっています。書き順を意識して書くことは、集中力と注意力を自然と育むことにつながります。
順序を守って書くことで、全体のバランスが整います。最初は意識して取り組まないとできないことですが、繰り返すうちに体が覚え、次第に自然な流れで書けるようになります。このプロセスが「考えて行動する力」や「丁寧さ」を育みます。
そして漢字をバランスよく書くということは、マスに入る字の大きさ、画数の多さ、辺とつくりなどのバランスをしっかりと見て考えて書くことで綺麗になる。
こうして「さんすう」からでなくても、空間認知能力・思考力は養われるのです。
4. 数字の書き順も同じくらい大切
日本語の文字に比べて軽視されがちな数字の書き順ですが、これも正しく書くことが非常に重要です。たとえば「5」や「9」は、書き順を間違えると形が崩れやすく、他の数字と見間違いやすくなります。
「0」「6」もどっちを書いているのか分からない生徒さんがいますが、今後の筆記テストやノート記述において、誰が見ても読みやすい数字を書くことは、大きな意味を持ちます。
5. 書き順を教えることの意義とは?
「結果」より「過程」を大切に
幼児教育においては、「上手に書けたか」よりも「どうやって書いたか」を重視することが大切です。たとえ形が少し崩れていても、書き順を守って丁寧に書いていれば、それは大きな成長の証です。書き順の正しさを評価し、認めてあげることで、子どもは自信を持ち、より意欲的に学習に取り組むようになります。
そして、注意してあげてほしい点があります。
ひらがなを書けるようになった子どもたちは、今度は自分の名前を漢字で書きたくなります。
その時「形」だけを重視し「書き順」を無視してしまうと、それが後々クセになってしまいます。
何事も最初が肝心。どうしても時間がなくて、「形」だけ合っていれば「書けた」となりがちですが、ここで「書き順」をしっかりと見てあげてください。
クセになってしまったものを、後から修正するのは大人の私たちでも大変なことです。
実際私も書き順には自信がありますが、それでも誤って覚えてしまっている漢字が多数あります。
「漢字検定」を必須としている学校もある中、書き順でもう一度覚えなおす時間はもったいない!
なので、最初に正しい「書き順」で練習しましょう。
6. ご家庭・教育現場での工夫
1. 書き順つきのひらがな・漢字表を使う
視覚的に「どの順で書くのか」がわかるポスターやカードは、子どもにとって非常にわかりやすい学習ツールです。指でなぞったり、空書きをしたりすることから始めると、手の動きがスムーズに育ちます。
2. 書き順をリズムにのせて
「いちはらって~、にでとめる~♪」といった具合に、書き順を歌やリズムにのせて教えると、楽しみながら覚えられる子もいます。ごっこ遊びの延長として取り入れることで、学びが自然なものになります。
この時、体を大きく使って大げさに書くこともオススメです!
7. 書き順は「学びの姿勢」を育てる入り口
正しい書き順を丁寧に学ぶことは、単に「きれいな字を書くため」だけではありません。それは、物事を順序立てて理解し、丁寧に取り組むという「学びの姿勢」を養う第一歩でもあります。
急いで書いて崩れてしまったり、好きなように書いて習慣になってしまう前に、幼児期のうちから「ゆっくり、ていねいに、正しく」という価値観を身につけることは、子どものその後の学びにおいて大きな財産となっていくと考えます。
終わりに
幼児教育における「書き順」は、どこか忘れられがち。
小さなことのようでいて、実はとても大きな意味を持つ学びの要素です。ひらがな、漢字、数字、それぞれに定められた順序に沿って書くことを通じて、子どもたちは「書くことの楽しさ」と「学ぶことの土台」を育んでいきます。
ご家庭でも、教育の現場でも、焦らず、楽しく、丁寧に書き順を伝えていきましょう。それが、子どもたちの未来の「言葉」と「学び」の力を育てる、確かな第一歩になるはずです。