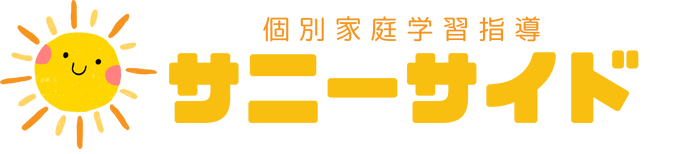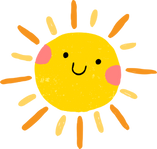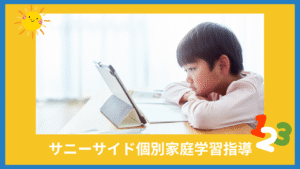仕事上、学校の宿題を見る機会が多々あります。誰もが経験した漢字ドリルノート。しかしよく見ると、同じ学年でもその仕上がりには大きな差があります。ある子はマスの中心に整った字を書けるのに対し、ある子は「頭でっかち」な字になったり、偏や旁(つくり)のバランスが極端に崩れていたり。中には、マスからはみ出すほど大きく、あるいは極端に小さく書く子もいます。
こうした子どもたちの「字のバランスの悪さ」に対し、指導者や保護者はときに「練習不足」や「不器用さ」として片付けてしまいがちです。しかし、書字のバランスには脳の発達段階や空間認知能力、そして運動機能の連携が大きく関わっており、必ずしも本人の努力や性格の問題とは限りません。
書字能力とは「総合的な脳の働き」である
まず押さえておきたいのは、「文字を書く」という行為が、単なる手先の運動ではなく、脳のさまざまな領域が連携する複雑な作業であるという点です。
具体的には以下のような機能が関与しています:
- 視覚認知:お手本やマスの形を視覚的に正確に捉える力
- 空間認識能力:形や位置関係を把握し、全体のバランスを判断する力
- 運動計画と実行:頭の中で思い描いた形を、手先を使って再現する力
- 微細運動能力(巧緻性):鉛筆をコントロールする手の細かな動き
このうち、特にマスの中に正しく字を配置する力には空間認知能力と視覚–運動統合能力が深く関係しています。
空間認知はいつ発達するのか?
空間認知とは、物の大きさ・形・位置・方向などを把握する力です。この能力は1月の投稿でもありますが、乳幼児期から少しずつ発達しますが、小学校低学年のうちはまだ未成熟な段階にあります。特に「文字をマスの中に収める」「形を模倣する」などの課題は、空間認知が安定しないと難しく感じる子どもも多いのです。
子どもによっては、空間認知の発達にばらつきがあるため、
- 偏だけがやたら大きい
- 上部に寄りすぎたり、逆に下部に寄りすぎたりしてしまう
- すべての文字が傾いてしまう
といった特徴的な書き方になることがあります。これは決して「いいかげんに書いている」わけではなく、空間把握の難しさからくるものなのです。
「異常」ではなく「発達途中」の可能性
保護者の中には「うちの子、何か発達に問題があるのでは…?」と心配される方も少なくありません。確かに、発達性協調運動障害(DCD)や学習障害(LD)の一部には、書字困難を伴うことがあります。しかし、字がうまく書けない=即、脳の異常というわけではありません。
ポイントは、「生活全体に支障を来しているか」「年齢相応の発達から大きく遅れているか」を見ること。例えば、
- 書くこと以外の場面(折り紙、工作、運動など)でも極端に不器用
- 文字以外にも、図形模写やパズルが極端に苦手
- 文章が書けない、板書ができない、漢字を極端に覚えられない
などのケースでは専門機関の評価が望ましいですが、ただ字が不格好だったり、マスにうまく収まらなかったりするだけなら、発達段階の問題であることがほとんどです。
バランスの悪さには「見方」の練習が必要
では、バランスが悪く字を書いてしまう子どもには、どのようなアプローチが有効なのでしょうか。大切なのは、単に「きれいに書きなさい」と繰り返すのではなく、「見る力」と「イメージする力」を育てる指導を取り入れることです。
1. 模写ではなく「観察」に重点を置く
お手本を見て書く場面では、「この字のどこが中心かな?」「どの辺が広い?」「上下左右のバランスは?」といった問いかけを通じて、「よく見る」ことを意識させることが大切です。視覚的な注意を引き出すだけでも、字の構成を把握しやすくなります。
2. 「マス割り図」を使って視覚化する
文字のバランスをとる練習として、小学校の漢字で使われている四分割したマスノートを使って「どこにどの部首が入るか」を視覚的に確認させる方法もあります。空間を意識させることで、位置の感覚が養われます。
3. 書く前に「指で空書き」してイメージをつくる
実際に書く前に、指で空中に大きく文字をなぞらせたり、空書きをさせたりすると、運動計画と視覚の連携がスムーズになります。これにより、頭の中で文字の形をしっかりイメージする習慣がつきます。
この時、大事になってくるのは前回の投稿にもあるように、「書き順」がカギになります。
4. 自分の字を見て「どこが変だったか」を考える
書いた後は、「この字のバランス、どうだった?」と自分で客観視する練習も効果的です。他人の字と見比べたり、過去の自分の字と比べたりすることで、視覚フィードバックを取り入れる力が養われます。
だんだんと書きながら「あ。このままだと綺麗に収まらない」と判断し、自分で気づき書き直すことができます。
その時は、「まだ書けない」よりも、「自分で気づけた」というところに着目し、褒めてあげましょう。
教材や遊びから自然に力をつける
また、書字に直接関係しない活動の中にも、空間認知や微細運動を養うチャンスはたくさんあります。
- パズルやブロック遊び
- 間違い探しや迷路
- 折り紙、ぬりえ、点つなぎ
- 粘土や積み木での制作遊び
こうした遊びの中で、「形を見る」「手で表現する」経験を繰り返すことが、結果として文字のバランス感覚にもつながるのです。
決して「うまく書けない」=「練習」ではなく、こういった違うアプローチを楽しみながらしていくことで、知らないうちに上手に書けるようになってたなんてこと、たくさんあります。
その子その子によって、発達の時期もかかる時間も異なります。
親が焦らないこと。それが大事なのではないでしょうか。
最後に:上手に書けなくても、「書きたい気持ち」を大切に
子どもにとって、文字を書くことはまだまだ「難しいスキル」です。それでも一生懸命にマスの中に字を入れようとしている姿は、見る側にとって微笑ましくも、健気なものです。
教師や親が「もっときれいに」「ちゃんとマスの中に書いて」と言いたくなる気持ちもよく分かりますが、上達の鍵は「書きたい気持ち」を伸ばすことにあります。必要なのは、失敗を責めることではなく、子ども自身が「上手になってきた!」と感じられるような支援なのです。
書字のバランスが悪いという現象の背景には、さまざまな発達段階の要素が絡んでいます。だからこそ、その子の視点に立ち、「見る力」と「描く力」が自然に育つような、温かく工夫されたアプローチをしていきたいものです。