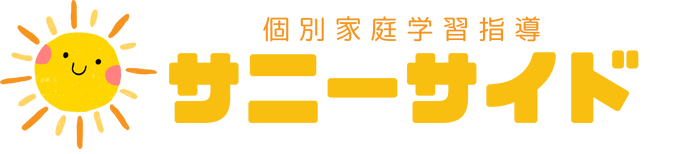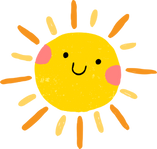現代の公園や家庭の風景には、かつてとは違った「遊び」の姿が見られるようになりました。幼い子どもたちが静かにタブレットを操作し、動画を眺めたり、知育アプリに夢中になったりする光景は、もはや珍しくないですよね。育児を助ける便利な道具として、スマートフォンやタブレットは現代の子育てに深く浸透しています。しかし、その一方で、「遊び」の質や子どもたちの成長に、何か見落としていることはないのでしょうか?
偏った意見ではなく、それぞれの良さををバランスよく「利用する」ことが今の私たちには必要なのではないかと考えます。今回はそんなお話をさせていただきました。ぜひ皆様も一緒に考えてみませんか?
スマホ・タブレットの登場で変わる幼児の遊び
スマホやタブレットが子どもに与える影響については、さまざまな研究が進められています。その利便性は高く、特に共働き世帯やワンオペ育児中の家庭では「静かにしていてくれる時間」を確保できる心強いツールでもあります。
そして教育においても効率よく分かりやすく勉強することもできます。
【メリット】
- 知育コンテンツの充実
年齢に応じた文字・数字・図形の認識を促すアプリ、英語の耳を育てる動画など、質の高い教育コンテンツが豊富。反復学習にも適しており、ゲーム感覚で学べる点は魅力的であると考えます。 - 集中力を養うツールにもなり得る
ある一定のタスクに集中して取り組むことで、注意力を育てる効果もあるのではないかと思います。タイマー機能と連携すれば、時間管理の習慣づけにも使えそうです。 - 場所や時間を問わず遊べる
電車の中や公共の場での待ち時間、車などの移動中でも手軽に遊べるのは親にとって大きな安心材料。忙しい日常の中で、親の負担を減らす役割も果たしています。
【デメリット】
- 視力・姿勢への悪影響
長時間の画面視聴は視力低下のリスクを高めます。また、下を向き続ける姿勢は、首や背中の筋肉発達にも偏りを生じやすくなり、身体的にも悪影響が生じます。 - 人との関わりが希薄に
画面を通じた遊びは基本的に一方向的な刺激で、相互的なやり取り、友達とのリアルな関わりが少なくなり、コミュニケーション能力や共感力の育成に影響する恐れがあると考えます。 - 感覚体験の不足
タブレット内の動画は驚くほどリアルです。それでも本物には勝てません。画面上では「触る」「嗅ぐ」「味わう」といった五感体験は得られにくく、手足を使って遊ぶことによる全身運動や、自然とのふれあいといった体験が減り、幼児教育においてとても大事な感覚体験ができなくなってしまいます。
昔ながらの遊びがもつ力
泥だんごづくり、折り紙、あやとり、鬼ごっこ、積み木、ままごとなど、私たちが幼いころに楽しんだ「昔ながらの遊び」は、今だからこそ、改めてその価値が見直されつつあります。
【メリット】
- 身体機能の発達
外遊びやごっこ遊びは、走る・跳ぶ・持つ・バランスを取るなどの身体運動を自然と促します。身体機能の発達に大事な幼児期には、こうした全身を使った遊びが不可欠であると考えます。 - 想像力と創造性を育てる
積み木で何かを作る、友達とごっこ遊びをする……道具がシンプルだからこそ、遊びの幅が広が、何かを「見立てる」力や物語を作る力は、創造性の基礎となり、ごっこ遊びなど、友達と一緒に遊ぶことでコミュニケーションが不可欠であり、遊びの中から人との関係性を築くことができます。 - 社会性と感情のコントロールを学ぶ
「順番を守る」「相手の気持ちを考える」「負けても我慢する」といった、タブレットでの一人遊びではなく、集団遊びの中でしか育まれない力があります。これらはのちの学級生活や社会生活における土台になります。 - 季節や自然とふれあう機会
虫取り、水遊び、落ち葉集めなど、自然と関わる遊びは感受性や好奇心を刺激し、それぞれの四季でどんな花が咲き、どんな虫がいて、どんな行事があるのかなど、自然を感じることで豊かな情緒を育てることができます。
特に小学校受験を視野に入れているご家庭では、プリント勉強ではなく実体験からの学習によって、より深くそして忘れにくいものになるでしょう。
【デメリット】
- 場所や時間の制限
天候や安全性、騒音などの理由から、自由に外で遊べない現代の住宅事情があるなど、昔ながらの遊びはハードルが高いものとなっているのも事実です。 - 親や大人の関わりが必要
一人で完結することが少ないため、保護者の付き添いや見守りが必要であり、忙しい現代の育児では、それが難しいという現実があります。
今、必要なのは「バランス」
スマホやタブレットを完全に否定するのではなく、その使用に「時間と内容の制限」を設けることが大事で、意識的に昔ながらの遊びの時間を日常に組み込むことが、子どもにとって身体的・精神的に最も健やかな成長を促すのではないかと思います。
たとえば、午前中は思い切り外で遊び、午後の休憩時間に10〜15分程度、知育アプリを楽しむ。こうした使い分けは、子どもにとっても親にとっても負担が少なく、自然な形でバランスを保つことができるのではないでしょうか。
また、保育園や幼稚園の現場でも園庭での泥遊びなど「昔ながらの遊び」を取り入れ直す動きが出てきています。幼稚園や小学校でも年齢の違う子どもたちを関わらせる縦割りでの行事を増やすなど、子どもたちの主体性や社会性を育てるような教育もなされています。
おわりに:遊びは「育ち」の鏡
幼い子どもにとって「遊び」は単なる暇つぶしではありません。それは世界を知る手段であり、身体と心を育てる重要な役割になっています。便利なテクノロジーと、原始的な体験のどちらも取り入れながら、子どもがのびのびと遊び、学び、育っていける環境を整えていくことが大切です。
タブレットは悪ではありません。方向が私たち大人に向くような使い方ではなく、子どもに向くように、そしてタブレットに「使われる」のではなく「使いこなす」ことで、両方を取り入れた素晴らしい「遊び」になると私は思います。