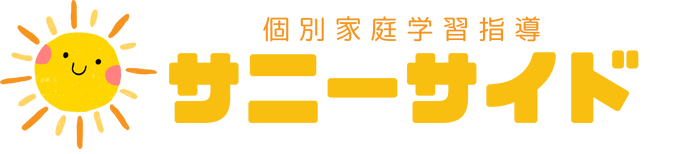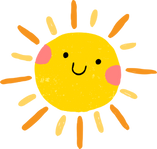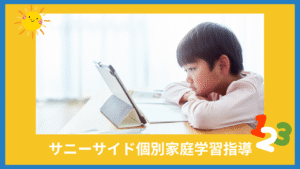近年、インテリアやライフスタイルにこだわる親世代が増えるなか、赤ちゃん向けの育児グッズやおもちゃ、衣類にも「デザイン性」が強く求められるようになってきました。特に人気なのが、ベージュやグレージュ、くすみピンクやくすみブルーなどの「アースカラー」や「くすみカラー」と呼ばれる落ち着いた色合いのアイテムたちです。SNSをのぞけば、シンプルで洗練されたベビールームやナチュラルカラーで統一されたおもちゃの投稿が並び、それらは美しく、整然としていて、「理想の育児」を象徴しているかのように映ります。
しかし、ここで立ち止まって考えてみたいのは、赤ちゃん自身にとって、それは本当に「良いもの」なのかという問いです。
赤ちゃんの視覚は未発達から始まる
生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、0.01〜0.02程度といわれています。ぼんやりとしか見えておらず、明暗の違いがようやく分かる程度。生後1ヶ月頃から徐々に焦点が合い始め、2ヶ月を過ぎると少しずつ色を認識できるようになります。
ただし、ここで重要なのは、**最初に認識されやすい色は「原色」や「コントラストの強い色」**であるということ。たとえば、赤・黒・白の配色は非常に認識されやすく、視覚の発達を助けるとされています。
実際に、多くの発達心理学の研究では「赤ちゃんの視覚的興味を引くにはビビッドカラーや高コントラストが有効」であるとされています。アメリカの発達心理学者ファンツ(Robert Fantz)の研究では、生後数週間の乳児でもパターンや色の違いを見分ける能力があり、単調な色よりもコントラストがはっきりしたものに長く注目することが分かっています。
「大人目線の美」と「赤ちゃんにとっての刺激」
一方で、アースカラーのおもちゃやグッズは、視覚的な刺激が少なく、落ち着いた印象を与えます。これは大人にとって「心地よい」空間づくりには向いていますが、赤ちゃんにとってはやや刺激が不足しがちかもしれません。
もちろん、部屋全体をビビッドカラーで彩る必要はありません。赤ちゃんの目に直接触れる、たとえばプレイマット、モビール、おもちゃ、絵本などには意図的にカラフルなアイテムを取り入れることが、脳への適切な刺激となります。
また、乳児期は視覚だけでなく、聴覚や触覚、嗅覚、味覚といった五感すべての感覚刺激が脳の成長を促す大事な時期。色彩に関しては、原色や補色の組み合わせを活用することで、視覚的なメリハリを与えることができます。
カラフル=ダサい?時代の価値観と「見た目の正しさ」
現代はSNS全盛の時代。多くの親が、我が子の日常をインスタグラムなどに投稿し、「おしゃれ」で「整った」写真をアップしています。そうした中で、くすみカラーのアイテムは「インテリアとして浮かない」「写真映えする」「大人も満足できる」点で人気を博しています。
しかしこの流行は、本来、赤ちゃんに必要とされる刺激や環境づくりよりも、「見た目の美しさ」が優先されてしまっていると感じます。
「カラフルなおもちゃはダサい」「チープに見える」といった美的価値観が赤ちゃんの発達にとって大切な選択肢を狭めてしまうのだとしたら、それは本末転倒です。
「発達」を中心にした育児環境づくりとは
育児用品を選ぶ際、インテリアとの調和や親の満足感を重視することも悪いことではありません。むしろ、育児は親の精神的安定が何より大切であり、整った空間がその助けになるなら、それも大きな意味を持ちます。
ですが、赤ちゃんの視点に立った環境づくりを同時に意識することも忘れないようにしたいものです。たとえば:
- プレイスペースだけは意図的にカラフルにする
- 絵本は色鮮やかなものを取り入れる
- おでかけ用のおもちゃにはビビッドカラーを選ぶ
こうした工夫をするだけで、「親の美意識」と「赤ちゃんの発達支援」は両立可能なのではないでしょうか?
赤ちゃんの発達に寄り添う「色」とのつきあい方
最終的に重要なのは、赤ちゃんが「見て」「触れて」「楽しめる」環境をつくること。それがひいては言葉の発達、好奇心、創造性など、様々な力の土台を築いていきます。
アースカラーやくすみカラーが悪いということではなく、赤ちゃんに必要な「視覚的刺激」とのバランスを見直してみること。おしゃれな空間づくりの中にも、ちょっとしたカラフルなアクセントを加えてみてください。
それが、赤ちゃんにとっても親にとっても、より豊かで心地よい育児時間につながっていくはずです。